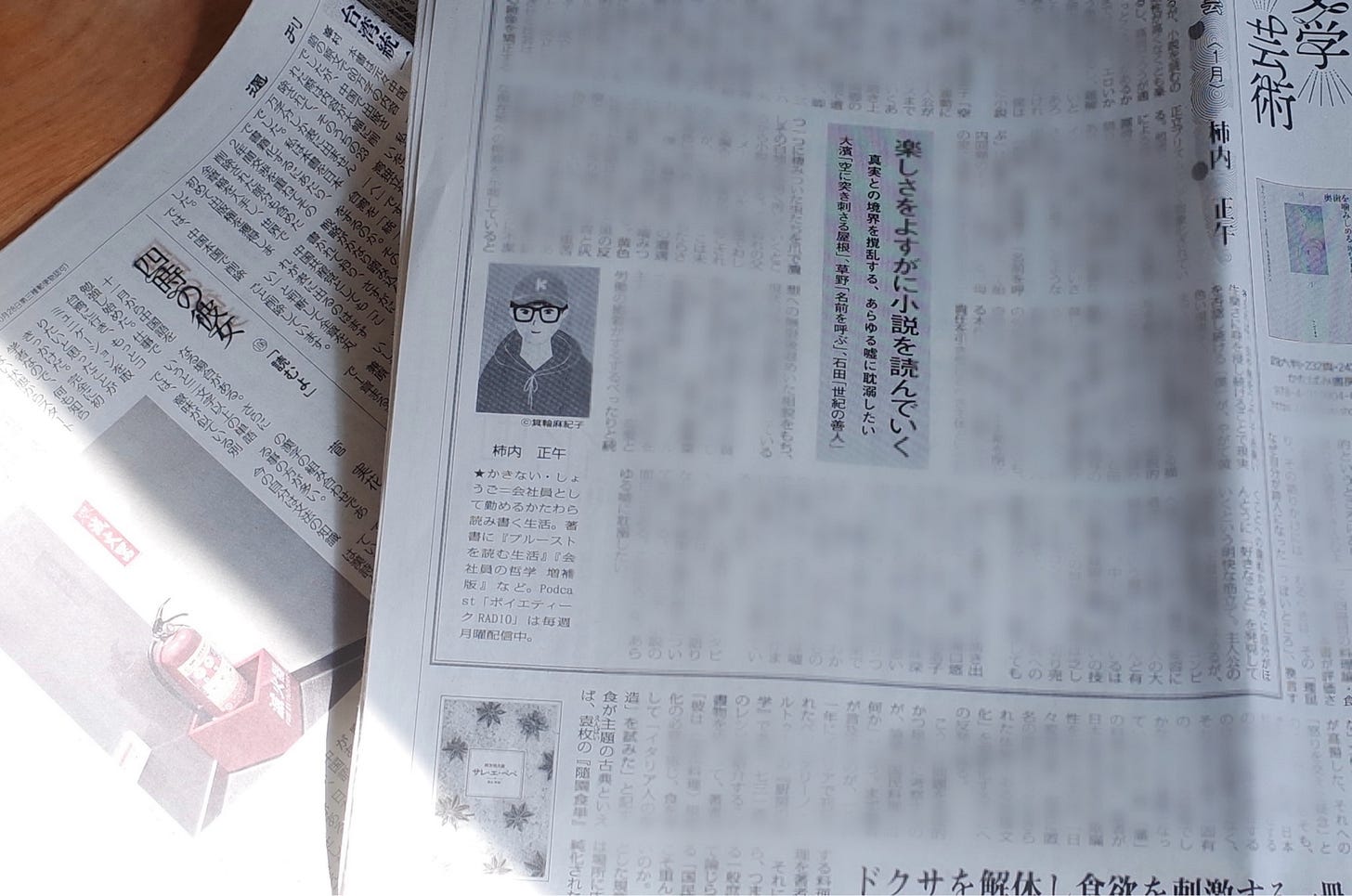文芸時評のB面 一月
はっじまるよ〜
今年は「週刊読書人」上で月一回の文芸時評を担当することになった。文字数は二千字程度ということなのでどうしたって溢れる。溢れたものについてもどこかでまとめたくなるかもしれないから、紙幅に収まりきらなかったものをこのメルマガもといニュースレター用に書き直して展開してみようと思う。「週刊読書人」掲載のものがトロの部分だとすると、こちらはアラ汁のようなものだ。いいと思ったものは極力「読書人」のほうで取り上げる。だからこちらでは褒めることより文句やぼやきのほうが多いかもしれない。それでは、どうぞ〜
B面(1月)
はじめに白状しておくけれど、僕はそこまで熱心な小説の読者ではない。だからこれから一年の仕事になる文芸時評なるものを引き受けたのは、僕がなにか現在の文芸シーンに通じており一家言を持っているだとか、これからの小説とはかくあるべしという大志があってのことではない。そういうものは読者の皆様のほうが持っているのではないかと思う。ぜひこの無知な評者へのご指導をお願いします。ではそんなずぶの素人がなぜこの仕事を引き受けたのか。ただ楽しそうだなと思っただけのことだ。
しかし文芸時評とはなんなのだろうか。文字通りに解すれば、文章表現の技芸を通じて時流を評することだ。通例ここでいう文章表現および技芸というのは狭義の意味で使われており、小説のことであると言ってよいようだ。問題は時流を評するというのは何かということで、まず時流とは小説を読み書くような人々の界隈における傾向に限られるのか、ひろく現行の社会システム上で起こる出来事まで射程に入れているものであるのか。また評するというのは値踏みするということであるが、ここで判断される価値の内実とはどんなものであるか。考えてみるとどうにも覚束ない。時流も評価も、大雑把にいって評者はどのような文脈を時代の風潮として考えているのかという問題であり態度表明である。
文芸時評というものの指示内容として明白に確定できるのは主に文芸誌に掲載された小説を扱うという、これまたひとつの慣例によって定められてきた要素だけである。いや、これもまた詩歌やブログ投稿といった小説外の文芸を含めない正当性はないわけで、いくらでも修正できそうではあるが、じっさい小説についてという内容で依頼をいただいたわけだし、いったん置いておこう。ひとまず小説ということにする。そうであれば、手掛かりは小説にしかない。ある小説を読むとき、その作品がどのような文脈上に自身を置いており、そこにおいてどのような価値の体系の補強ないしは破壊あるいは創造を試みているのか、という点を析出することを第一にめざすべきであり、そのうえで、その成否を判断できたら上々。そのような行為として文芸時評というものを扱ってみようと思う。
一月号は中年や老年の小説が目立った。老いをテーマにすると多くは陳腐に偏り過ぎるようで、書かれている内容に新規さはない。驚きなのはほぼ全ての作品において、年を重ねた作中人物たちが幼稚であることだ。角田光代「モンゴルの蓋」(『新潮』)は、そのような大人たちの幼稚さを冷徹に対象化する目を唯一有している作品だと感じた。人は年齢に関係なく常にしょうもないものであり、そのようなしょうもなさをわざわざ掬い取るのも小説なのだ。
俗っぽさをどう小説に導入するかという点ではスマートフォンの扱いに書く作品の設計思想が垣間見えるようだ。草野理恵子「名前を呼ぶ」(『文學界』)では唐突に放り込まれる「SNS」という語がほどよく没入を断ち切っているが、他作品でもスマートフォンの扱われ方が面白かった。小山田浩子「えらびて」(『新潮』)では「ちーちゃんのお母さんからのライン」の絵文字をアルファベットにひらく表現が光っていたし、村田沙耶香「無害ないきもの」(『文學界』)のようなディストピアめいた寓話にさらっと登場する「スマートフォン」での撮影の場面も可笑しい。
村田沙也加の短編はドイツ語、平野啓一郎「伊吹」(『新潮』)は中国語での発表された作品の日本語版だという。異言語への翻訳が先立つ作品の意義について考えた。海外文学の面白さは、異物としての言語が際立つからだ。ある言語体系に依存したほんらい通訳不能な思考や観念を無理やり既成の言語へと変換することを通して慣れ親しんだ言語運用の外側が顕れるからこそ、翻訳という営為は楽しい。そのような観点から見るならば、両作とも初めから翻訳の容易さを意識してか日本語の運用としては非常に穏当で、ローカルな面白さに乏しいとも言える。
小説というものにロマンチックな印象を持っている人は現代においては少数派であると思う一方で、まだまだ小説というものへの甘やかな幻想は根強いのかもしれないとも感じる。その甘やかさは小説を恥ずかしいもの、みっともないものとして考える心性を呼び起こしもして、じっさい小説はそういうものでもある。そもそもが古代中国において高級官僚が担う正当な歴史「大説」に対し、下っ端官僚たちの大したことのない世間話を指す言葉であったという小説は、いまもなお正史に対抗し、あるいはそれを補い、密やかに遊撃を仕掛ける稗史としてのいかがわしさを保持している。壮大な法螺の楽しさは円城塔「冥王の宴」(『新潮』)にあったが、これは連作の途中のようでこれだけだと食い足りなかった。井伏鱒二「小さな町」(『新潮』)の、何が書かれていないかにこそ比重が置かれる書きぶりに稗史としての矜持と洗練を見てもいい。「名前を呼ぶ」や大濱普美子「空に突き刺さる屋根」(『文學界』)は、小恥ずかしい文学っぽさ、半ば時代錯誤ないかがわしさを堂々と保持しているという点が好ましかった。
いかがわしい法螺である小説は、現在の社会通念とべったりし過ぎていると巷で交わされる噂話のよくできた議事録に留まり退屈だったりするが、だからといって浮世離れしていればそれでよいということでもない。嘘をつくのにも嘘をまことしやかに成立させるためのある種の強度というものが必要なのであり、そのような嘘を嘘のままにつきとおすための何ものかをどのように宿すかという工夫にこそ小説の楽しみは宿る。僕はこのような好みでもって各誌に目を通していくことになるだろうし、好みではないものに対しても、この凄さは無視できないとのけぞる喜びを期待している。
より本腰を入れて楽しく読んでいる時評の本編は「週刊読書人」に掲載されています。本屋さんで買えるはずです。通販やPDF版もあります。
WEBショップはこちら→ https://jinnet.dokushojin.com/products/3522-01_12_pdf